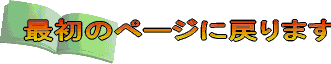號 |
発行年月日 | 西暦 | 筆者 | 題名 | 備考 |
| 1 | 昭和35年12月1日 | 1960 | 小汀 利得 | 分斷され支配されるな | |
| 田邊 萬平 | 字憎悪の妄執 | ||||
| 日夏耿之介氏口を噤むの辯 | |||||
森  外 外 |
假名遣に關する意見 [本文はここを] | 國語問題文獻(一) | |||
| 2 | 昭和36年2月1日 | 1961 | 木内 信胤 | 漢字と日本人の能率 | |
| 松本 洪 | 現代の病根 | ||||
| 高津 才次郎 | 不備不満不當の文字いぢり | ||||
| 山田 孝雄 | 文部省の假名遣改定案を論ず[本文はここを] | 國語問題文獻(二) | |||
| 3 | 昭和36年4月1日 | 1961 | 結城 錦一 | 縱書き横書きの心理學 | |
| 宇野 精一 | 刑法の表記改變に就いて | ||||
| 山田 孝雄 | 再び文部省の假名遣改定案に抗議す | 國語問題文獻(三) | |||
| 4 | 昭和36年6月1日 | 1961 | 御手洗 辰雄 | 國語審議會のあり方 | |
| 文部大臣への要望書・お伺ひ | |||||
| 芥川 龍之介 | 文部省の假名遣改定案について[本文はここを] | 國語問題文獻(四) | |||
| 5 | 昭和36年8月1日 | 1961 | 山本 健吉 | 話し言葉と表記法 | |
| 鹽田 良平 | 審議會脱退の辯 | ||||
| 田邊 萬平 | 天下の笑ひ | 随筆 | |||
| 福田 恆存 | ホンヤ・クーバコ・クービン | 随筆 | |||
| 研究調査小委員會の研究調査項目 | |||||
| 木下 杢太郎 | 假名遣の問題 | 國語問題文獻(五) | |||
| 特輯號 | 昭和36年9月1日 | 1961 | 田邊 萬平 | 開会に當りて | 講演會特輯 |
| 辰野 隆 | 國語愛について | ||||
| 小泉 信三 | 正しい國語の輕視と重視 | ||||
| 平林 たい子 | 國語と日常生活 | ||||
| 成瀬 正勝 | 明治以後の國字改良の問題點 | ||||
| 石井 勲 | 小学校における漢字教育について | ||||
| 大野 晋 | 國語政策について | ||||
| 6 | 昭和36年10月1日 | 1961 | 時枝 誠記 | 國語問題論議の一の重要な性格 | |
| 七理 重恵 | 香港幼稚園の漢字教育 | 随筆 | |||
| 木下 杢太郎 | 國字國語改良問題に對する管見(上) | 國語問題文獻(六) | |||
| 7 | 昭和36年12月1日 | 1961 | 山岸 徳平 | 常識的判斷の總合 | |
| 田中 西二郎 | 國語とイデオロギー | ||||
| 木下 杢太郎 | 國字國語改良問題に對する管見(下) | 國語問題文獻(六) | |||
| 8 | 昭和37年3月1日 | 1962 | 服部 嘉香 | 國語政策の正常化を望む | |
| 村松 嘉津 | 國語ローマ字化の一先例 | ||||
| 福田 恆存 | 講演會特輯 | ||||
| 三田村 篤志郎 | |||||
| 鹽田 良平 | |||||
| 宇野 精一 | |||||
| 村松 嘉津 | |||||
| 長谷川 才次 | |||||
| 時枝 誠記 | |||||
| 小汀 利得 | |||||
| 田邊 滿平 | |||||
| 9 | 昭和37年4月1日 | 1962 | 太田 青丘 | 最低線か最高線か | |
| 長澤 規矩也 | 當用漢字による表記の混亂 | ||||
| 伊藤正雄・金井透 | 聲 | ||||
| 松井 武男 | 國語問題時評「國語問題あれこれ」 | ||||
| 與謝野晶子 | 田中文相に呈す | ||||
| 10 | 昭和37年7月1日 | 1962 | 阿部 吉雄 | 漢字教育について | |
| 岩下 保 | 「新送りがな」は教育界の懸案解決になり得たか | ||||
| 古川 恒 | 日本語の文字印刷の現状と將來への見透し | ||||
| 松本 洪 | 中共文字のラテン化について | ||||
| 11 | 昭和37年8月1日 | 1962 | 澤柳 大五郎 | 國語問題の底に | |
| 鈴木 由次 | 國語教育の一問題 | ||||
| 野溝 七生子 | 思ひつくままに | ||||
| 本間 久雄 | 國語と傳統 | ||||
| 12 | 昭和37年10月1日 | 1962 | 福田 恆存 | 詩と修辭學 | |
| 進藤 純孝 | 簡と要 | ||||
| 萩野 貞樹 | 聲 | ||||
| 下別府 峰春 | 漢字指導の經過と所感 | ||||
| 13 | 昭和37年12月1日 | 1962 | 田邊 滿平 | 字義輕視の思想 | |
| 林 巨樹 | 國字政策の齎したもの | ||||
| 後藤 光邨 | 聲 | ||||
| 大泉 健二郎 | P音學説批判成立まで | ||||
| 14 | 昭和38年3月1日 | 1963 | 福田恆存 | 開會の辭 | 第四囘講演會特輯 |
| 石井 勳 | 漢字はやはり難しくなかつた | ||||
| 木内 信胤 | 漢字・經濟・これからの日本 | ||||
| 杉森久英 | 私の國語觀 | ||||
| 森田 たま | 國語教育について | ||||
| 成瀬 正勝 | 國語政策と國語問題 | ||||
| 岩下 保 | 國語問題の新情勢 | ||||
| 小汀 利得 | 閉會の辭 | ||||
| 15 | 昭和38年4月1日 | 1963 | 井上 萬壽藏 | 雜感片々 | |
| 小堀 杏奴 | 漢字制限と新假名遣ひ | ||||
| 柳 宗悦 | 假名書きの不便さ | ||||
| 高津 才次郎 | 新送りかな修正私案 | ||||
| 16 | 昭和38年6月1日 | 1963 | 市原 豐太 | クローデルの言葉 | |
| 近藤 祐康 | 國語表音化の背景と趨勢 | ||||
| 時枝 誠記 | 第六期國語審議會の成立とその課題 | ||||
| 竹内 輝芳 | 送假名に關する私見 | ||||
| 17 | 昭和38年8月1日 | 1963 | 長谷川 如是閑 | 日本人の國語の性能について | |
| 田所 義行 | 新古典主義小徑 | ||||
| 山崎 馨 | 聲 | ||||
| 羽根田 諦 | 皇室用語と<られ敬語> | ||||
| 18 | 昭和38年10月1日 | 1963 | 松本 洪 | 漢字とローマ字との比較 | |
| 倉橋 由美子 | 私の國語國字問題 | ||||
| 三潴 信吾 | 國語問題を何故問題とするか | ||||
| 石井 勲 | 龜田東小學校の漢字教育について | ||||
| 19 | 昭和38年12月1日 | 1963 | 時枝 誠記 | 國語審議會の報告を讀んで | |
| 第六期國語審議會報告書について | |||||
| 大垣 敏雄 | 聲 | ||||
| 清田 清 | 私の國語國字問題 | ||||
| 20 | 昭和39年3月1日 | 1964 | 宇野 精一 | 開會の辭 | 特輯 |
| 朝海 浩一朗 | 外國より歸りて感あり | ||||
| 市原 豐太 | 文化と國語 | ||||
| 澤柳 大五郎 | やさしい・むずかしい・合理・不合理といふことに就いて | ||||
| 海音寺 潮五郎 | 誰にも權利はない | ||||
| 小汀 利得 | 閉會の辭 |