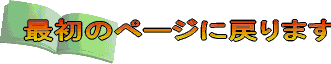
『國語國字』第161號〜第180號
| 號 | 発行年月日 | 西暦 | 筆者 | 題名 | 備考 |
| 161 | 平成6年2月1日 | 1994 | 土屋 秀宇 | 公立小學校における石井式漢字教育の挑戰 | 第五十一囘講演會記録 |
| 原田 種成 | 「康煕字典」の字形には誤りが多い | ||||
| 筧 泰彦 | 日本人の宗教と日本語 | ||||
| 石井 勳 | 閉會の辭 | ||||
| 岩下 保 | 追悼・松井武男先生の思ひ出 | ||||
| 162 | 平成6年5月1日 | 1994 | 木内 信胤 | 遺稿 | 追悼・木内信胤會長 |
| 宇野 精一 | 木内さんの思ひ出 | ||||
| 筧 泰彦 | 木内信胤先生を偲んで | ||||
| 村尾 次郎 | 木内信胤翁管窺 | ||||
| 石井 勳 | 木内先生を偲ぶ | ||||
| 三潴 信吾 | 「温故知新」の御努力に敬服 | ||||
| 新井 寛 | 追悼・木内信胤先生のこと | ||||
| 林 巨樹 | 一即一切、一切即一 | ||||
| 小田村 四郎 | 木内信胤先生を偲ぶ | ||||
| 關正臣 | 思ひ出す事など | ||||
| 不破 淑子 | 思ひ出すこと等 | ||||
| 赤松 一男 | 同じ光景を見た | ||||
| 岩下 保 | 偉大なる思想と足跡(一) | ||||
| 163 | 平成6年10月1日 | 1994 | 石井 勳 | 漢字文化圈の最近の動向 | 第五十二囘講演會記録 |
| 三橋 敦子 | 日本語のルーツをさぐる | 司會:岩下 保 | |||
| 宇野 精一 | 所感(話し言葉について) | ||||
| 林 巨樹 | 閉會の辭 | ||||
| 164 | 平成7年3月1日 | 1995 | 鈴木 智子 | 小學生に漢詩を教へて | 第五十三囘講演會記録 |
| 田中 瑛也 | 地中海文明の源流 | 司會:岩下 保 | |||
| 石川 忠久 | 中國に於ける漢詩の現況 | ||||
| 宇野 精一 | 言葉の問題 | ||||
| 新井 寛 | 閉會の辭 | ||||
| 165 | 平成7年11月1日 | 1995 | 山下 宏一 | 幼稚園兒に古典を教へて | 第五十四囘講演會記録 |
| 林 巨樹 | 「假名遣ちかみち」を繞つて | 司會:岩下 保 | |||
| 阿川 弘之 | 志賀直哉先生のことなど | ||||
| 宇野 精一 | 漢字文化圈 | ||||
| 三潴 信吾 | 閉會の辭 | ||||
| 166 | 平成8年3月1日 | 1996 | 岩下 保 | 開會に際して | 第五十五囘講演會記録 |
| 林 巨樹 | 移りゆく日本語と辭書 | ||||
| 三輪 晃久 | われら地球人 | ||||
| 村尾 次郎 | 由緒ある地名の保存 | ||||
| 新井 寛 | 閉會の辭 | ||||
| 167 | 平成8年9月1日 | 1996 | 大橋 伊佐男 | 中學校に於ける古典教育の現状 | 第五十六囘講演會記録 |
| 半田 一郎 | 沖繩語の重み | 司會:岩下 保 | |||
| 宇野 精一 | 國語に關する断想 | ||||
| 石井 勳 | 閉會の辭 | ||||
| 168 | 平成9年3月1日 | 1997 | 新井 寛 | 開會の辭 | 第五十七囘講演會記録 |
| 前川 孝志 | 高等學校に於ける國語教育について | 司會:萩野 貞樹 | |||
| 山口 康助 | 國語問題管見 −中教審の姿勢を問ふ− | ||||
| 宇野 精一 | いま氣になってゐること | ||||
| 169 | 平成9年9月1日 | 1997 | 新井 寛 | 國語問題協議會38年 これからのこと −岩下事務局長を偲んで− | 第五十八囘講演會記録 |
| 萩野 貞樹 | 歴史的假名遣と若者たち | 司會:林 巨樹 | |||
| 石井 勳 | 漢字の歴史 | ||||
| 宇野 精一 | 教科書のことなど | ||||
| 170 | 平成10年3月1日 | 1998 | 杜 聰明 | 漢字が過去と未來の扉を開く | 第五十九囘講演會記録 |
| 倉島 長正 | 近代國語辭典の歩み | 司會:新井 寛 | |||
| 宇野 精一 | 送りがなのことなど | ||||
| 171 | 平成10年9月1日 | 1998 | 林 巨樹 | 澤柳 第五郎さんを偲ぶ | 特輯:逝きし人々 |
| 石井 勳 | 落合欽吾先生の事 | ||||
| 宇野 精一 | 太田青丘の追想 | ||||
| 萩野 貞樹 | 岩下保さんのこと | ||||
| 岩下 明 | 父と國語問題協議會 | ||||
| 新井 寛 | 小堀杏奴さんの思ひ出 | ||||
| 172 | 平成10年9月20日 | 1998 | ダニエル・ロング | 日本語の國際化 | 第六十囘講演會記録 |
| 石井 勳 | 漢字の國際化 | 司會:新井 寛 | |||
| 宇野 精一 | 外國の地名人名の表記について | ||||
| 173 | 平成11年1月30日 | 1999 | 桂 重俊 | コンピューター國文學の展開について | 第六十一囘講演會記録 |
| 高井 有一 | 小説家の立場から國語問題を考へる | 司會:新井 寛 | |||
| 宇野 精一 | 今囘の國語審議會の經過報告について | ||||
| 174 | 平成11年10月8日 | 1999 | 新井 寛 | 開會の辭−創立四十周年を迎へるに際して− | 第六十二囘講演會記録 |
| 林 巨樹 | 假名の音価・假名遣縁起 | 司會:新井 寛 | |||
| 村松 定孝 | 泉鏡花と言葉 | ||||
| 宇野 精一 | 國語教育について | ||||
| 175 | 平成12年11月27日 | 2000 | 新井 寛 | 開會の辭−本會の使命と全國講演について− | 第六十四囘講演會記録 |
| 瀧澤 幸助 | 占領政策と國語政策 | 司會:新井 寛 | |||
| 萩野 貞樹 | 江戸辯と東北辯と | ||||
| 山口 康助 | 青少年の心を培ふ歌作について | ||||
| 宇野 精一 | 古典教育について | ||||
| 176 | 平成13年5月27日 | 2001 | 新井 寛 | 開會の辭 | 第六十五囘講演會記録 |
| ピーター・ピーダーセン | 言葉と文化の共創 −日本語のエコロジー | ||||
| 成瀬 櫻桃子 | 現代俳句と國語について | ||||
| 桶谷 秀昭 | 國語問題と戰後日本の精神状況 | ||||
| 宇野 精一 | 言葉の表記について | ||||
| 177 | 平成14年6月10日 | 2002 | 新井 寛 | 開會の辭 | 特別號−契冲歿後三百年・宣長歿後二百年記念 |
| 林 巨樹 | 契冲・宣長について思ふこと | ||||
| 鈴木 丹士郎 | ことばの正濫 | ||||
| 市川 浩 | 電腦時代を支へる契冲・宣長の偉業 | ||||
| 高池 勝彦 | 閉會の辭 | ||||
| 178 | 平成15年3月27日 | 2003 | 新井 寛 | 開會の辭 | 第六十六囘講演會記録 |
| 茂木 弘道 | 「小學校に英語は必要ない。」とは | ||||
| 金井 透 | 國語正常化への探求 | ||||
| 白井 浩司 | 飜譯と言葉の問題 ―日本とフランス― | ||||
| 宇野 精一 | 小・中學校の國語教育 | ||||
| 179 | 平成15年8月18日 | 2003 | 新井 寛 | 開會の辭 ―教育と教科書問題など― | 第六十七囘講演會記録(東京、平成十三年十月二十七日) |
| 高井 和大 | 『もつたいない』を死語とする勿れ | ||||
| 石井 公一郎 | 『平成新選百人一首』について | ||||
| 藤原 正彦 | 國語の重要性について | ||||
| 宇野 精一 | いろはと假名遣について | ||||
| 180 | 平成16年5月27日 | 2004 | 小堀 桂一郎 | 國歌 君が代 | 『平成新選百人一首』出版記念講演會記録 |
| 歌、讀み人、出典、解説者 | 平成新選百人一首 | ||||
| 篠 弘 | 現代短歌の魅力 | 第六十八囘講演會(東京、平成十四年五月十八日) | |||
| 岡野 弘彦 | 日本人と和歌 | ||||
| 田中 佩刀 | 古典を讀む | ||||
| 宇野 精一 | 教育の現状批判 | ||||
| 早川 聞多 | 浮世繪と古歌 | 第六十九囘講演會(京都、平成十四年六月二十九日) | |||
| 小堀 桂一郎 | 古今の和歌に表れた推移の感覺 | ||||
| 吉原 榮徳 | 契冲研究と國語の問題 | ||||
| 樺島 忠夫 | 「表外文字字體表」について | ||||
| 桂 重俊 | 和歌短歌データベースの檢索および構築 | 第七十囘講演會(仙臺、平成十四年十月五日) | |||
| 小堀 桂一郎 | 物語と和歌の結びつきについて | ||||
| 片野 達郎 | 中世和歌の美意識 |